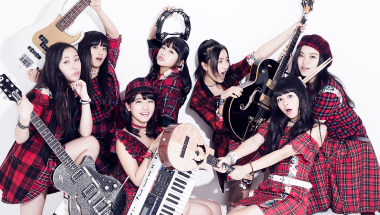三柴:今までは、専用レコーダーでないとダメだって勝手に思い込んでいて、なかなかDAWに踏み切れなかったんです。ずっと「SONARは音がいいよ」とは聞いていたんですが、僕自身がPCに疎いですし、ロックの現場などで、DAWの音を聴いても、あまり音がいいとは思えなくて。「THE 金鶴」は、結成時からハイ・クオリティな音で音楽をお届けしたいという気持ちがあって、だからシンセなども、最新のものを使ってきました。でも今回、思い切って踏み込んでみたら、すごく簡単だし、音もよくて、ビックリしました。
佐々木:僕らの世代って、8トラックMTRくらいから制作を始めて、スタジオでDAWシステムがフリーズする現場を何度も体験してきたんです。特に彼は、MIDIではなく、全部、手弾きでオーディオ録音しますから、タイトな日程でPCトラブルがあると大変なんですね。だから専用レコーダーでないと、信用できなかったんです。ただ今は、コンピューターも発達して、SONARもどんどん進化したことで、トラック数だとか、かえって専用レコーダーの限界が見えて来て。それでこのタイミングでSONARを導入したんですが、これは本当に助かりましたね。
三柴:導入したのは、昨年の秋頃だったんですが、映画の映像が届いたのが今年に入ってからだったので、短期間で、すべての作業を行いました。それまでの期間に、使い方を覚えて、曲想が浮かんだら、すべてのシンセを立ち上げて、10分後には録音を始めるといった作業でした。こんなに楽に制作を進められるとは思いませんでした。

三柴:いくら24ビット/192kHz録音と言っても、AD/DAコンバーターがよくないと、音が悪くなりますよね。DAWを始めるにあたって、ずっとそこが気になっていたんですが、OCTA-CAPTUREは、すごくよかったです。実際に音を確かめて、佐々木さんにもOKを貰って、導入を決めました。
佐々木:今回の制作で一番ビックリしたのが、OCTA-CAPTUREのよさでした。
三柴:しかもこれには、オート・センス機能があるじゃないですか。佐々木さんがいなくて、自分で録音する時は、これが絶対に必要で。
三柴:すごく難しいです。よく佐々木さんから怒られるんです。「こういうフレーズです」って、一度試しに弾いて、さあ本番を録ろうとなると、ものすごく演奏に力が入っちゃって、全部の音が歪んでしまって(笑)。
佐々木:プロ・ミュージシャンも、本番は音がデカくなるんですよ。もちろん、レコーディング・スタジオであればリミッターなどを使えますが、自宅だとなかなかそうはいきませんから。そういった面も含めて、音のよさはもちろん、OCTA-CAPTUREがあったおかげで、ストレスなく作業ができました。30年間一緒にやってきて、今回初めて、彼が自分で録音までしてくれたから、僕の作業も半分で済んだし(笑)。
三柴:カセットMTRの時代から、僕が自分で録音すると、音が割れて使い物になりませんでしたから(笑)。

三柴:そうですね。あと、INTEGRA-7の存在も大きかったですね。昔は、自宅ではデモ程度のものしか作れないことが当たり前でした。特に今回、INTEGRA-7やV-Synth GTで鳴らしている音って、ほとんどが生楽器なんですよ。この映画は、1960年代の“家”や“家族”をテーマにした作品でしたから、生楽器でいこうと決めていたんです。そういう音って、以前なら実際にプレイヤーを呼ばないと録音できなかったわけです。ただ、最近の映画音楽の制作では、予算や時間的な問題もありますし、もしプレイヤーを呼べても、なかなか皆さんが、音楽に夢中になって演奏してくれないという事をとても残念に思っていて。
佐々木:だから結局、思い通りの音楽にできないことが多いんです。
三柴:こういう時に演奏してもらう方々って、クラシック音楽を学んできた人たちなので、初見で演奏できるんですよ。だから、録音のギリギリまで携帯電話をいじっていて、本番が始まったら、パッと弾いて、帰っていく。音程が合っていなくても、現場の人は「OK!」と言って、後からコンピューター上でピッチを直していくわけです。そうすると、音源以上に機械っぽい音になってしまうんですよ。やっぱり一流のオーケストラって、尊敬する指揮者の元で、一生懸命、感情を込めて演奏するのが一番いいわけで、ただでも、僕らがそれを映画音楽制作で実現するのは難しい。そういう時に、INTEGRA-7の存在は、本当にありがたかったですね。
佐々木:彼は“オーケストラ・マニア”なんですよ。だから、それぞれの楽器の弾き方まで再現してINTEGRA-7で演奏するので、本当にその楽器のように聴こえるんです。おそらく音だけ聴いたら、生楽器なのかINTEGRA-7なのか、聴き分けられないと思いますよ。
三柴:僕以上に、メンバーのClaraは生楽器を熟知していて、「バイオリンのビブラートはここからかかり始める」とか、音色をすごく細かくカスタマイズするんです。僕自身は、ホルン系の音色がとても気に入って、イングリッシュ・ホルンとフレンチ・ホルンを使い分けて鳴らしました。あと、マリンバやビブラフォンのリアルさは、尋常じゃないですね。実機を叩くと分かるんですが、こういう楽器の音って、お腹に響くんですよ。そこまで表現されていて、あまりのリアルさに、ちょっと気持ち悪いくらいでした(笑)。
佐々木:逆にリアルすぎるので、音像に奥行感を加えたり、あえて質感を少しだけローファイにするのが、ミックスでのポイントでした。マリンバをホールの反響板の中で叩くと、必ずディレイ音が生じるんです。ですから、リバーブだけではなくてディレイも必要で、そうすることで、よりリアルに聴こえるんです。INTEGRA-7の音は、生楽器が発する直接音として非常にリアルなので、それをミックス時に、客席で聴こえるリアルな奥行感をシミュレーションするために、SONARのプラグインを活用しました。
佐々木:一番多かったのが、ラストの「Starting Over」かな? これがステレオ11パートなので、合計22トラックですね。サウンド・トラックの場合、あまり多くの音数で埋めてしまうと、一番大事な台詞の邪魔をしてしまうことがあるので、音数が多くなり過ぎないようにということは、意識しています。
三柴:この曲は、エンディング・テーマが流れる直前のトラックで、西村知美さんが演じる主人公“種”のテーマなんです。ストリングスに重なって入ってくるメロディは、INTEGRA-7のフレンチ・ホルン(SN-A PRST 0230 French Horn)を使っています。最後に出てくるティンパニ(SN-A PRST 0181 Timpani)は、単音とロールで、別トラックに分けて録りました。このティンパニが、これまた驚くほど生っぽいんです。ロールも、実際の映像を見ながら、ベンダー・レバーでリアルタイムにコントロールしています。
三柴:フレンチ・ホルンも、フルートも、ティンパニも、全部、映像を見ながらの生演奏です。しかも、最初に佐々木さんがおっしゃったように、MIDIは使わずに、そのままオーディオで録音しているんですよ。フレンチ・ホルンとマリンバなどで演奏した「Choker」も、聴いていただけると面白いと思います。もう完全に“生”な感じです。演奏自体も、クリックなどは使わずに、「せーの!」でやっていますから。
三柴:そうです。「Pavane」は、場面転換用に作った短い曲で、これは、ラヴェルの「亡き王女のためのパヴァーヌ」のフレーズを、僕がハープ(SN-A PRST 0183 Harp)、ClaraがFantom-Gのテルミンと、2人で演奏しました。このハープの表現力もすごく豊かでしたね。あと「Knot」は、ある登場人物が死にそうだという知らせを受けて、慌て始める場面の音楽です。マリンバ(SN-A PRST 0171 Marinba Soft)で始まるんですが、その心理状態を表現するために、映像を見ながらだんだんとアッチェルしていって、病院に駆けつけてバッとシーンに切り替わった瞬間に、マリンバからストリングス(SN-A PRST 0203 StringSect 1/SN-A PRST 0204 StringSect 2)のフレーズに変わるんです。
佐々木:ミックスでは、TL-64チューブ・レベラーなどを使って、落ち着いた質感にしています。
三柴:これは、バイオリン(SN-A PRST 0211 String Pizz)の低い音程を、S2ボタンを使ってピチカートで鳴らしています。すごくリアルですよね。こういった、「せーの!」で演奏するレコーディングで、実はA-300PROのコントローラー機能が、とても役立ったんです。
三柴:僕らは全部手弾きで録りますから、弾き間違えた時や、もう1回弾き直したいと思った時に、すぐに録り直したいんです。その際に、A-300PROのボタンで、SONARの再生や録音、停止といったトランスポーズ操作が素早く行えたので、ストレスなくレコーディングを進められました。それに、編集でボリュームのオートメーションを書く際も、例えば、直線的にフェード・アウトさせるのではなく、耳で聴きながら、A-300PROのスライダーを下げていく方が、自然な表現ができるんですよ。そういう時にも、A-300PROはとても便利でしたね。
三柴:以前の音源、分かりやすく言えば、強弱で音色が数段階ほど変化する音源であれば、例えばホルンのフレーズをMIDI録音して、後からトロンボーンに差し替えても、まあ大丈夫だったんですよ。ところがINTEGRA-7くらいに表現力が繊細になると、音色を差し替えることで、ニュアンスがまったく変わってしまうんです。ホルンからトロンボーンに音色を変えただけではトロンボーンの演奏にはならなくて、トロンボーンの演奏として、弾き直すしかないんです。
佐々木:逆に言えば、INTEGRA-7って、MIDIでは伝えられないくらいの表現力を持っているっていうことなんですよ。
三柴:例えば、結婚式のシーンで流れる「Wedding」という曲があって、これはグノー「アヴェ・マリア」と、ワーグナー「結婚行進曲」のメロディをつなげたものですが、「結婚行進曲」のフレーズを鳴らすトランペット(SN-A PRST 0218 Trumpet 1)などは、本当に生々しく“吹いて”ます。そういった、それぞれの楽器音の表現力まで、ぜひ耳を傾けて聴いてみて欲しいですね。

三柴:それぞれの音色が本当に素晴らしいクオリティなので、特にINTEGRA-7を生楽器の目的に使うなら、その楽器の奏法や表現力を本当に分かっている人こそ、このすごさに驚くのではないでしょうか。打ち込み用音源としてだけ使うには、非常にもったいないと思います。
佐々木:ただ、あまりクオリティが高過ぎて、普通に録ると音が生っぽくなり過ぎるので、ミックスでは、それを“どう汚すか”という点を考えました。

佐々木:この映画は、先ほど話が出たように、少し時代が古いものでしたから、音源そのままの音だとクオリティが高過ぎて、その場面に流れる音楽としては、雰囲気がそぐわなかったんです。だから、テープ・シミュレーターを通したり、ビンテージのコンプレッサーで昔っぽい質感にするといった処理は、かなりやりましたね。しかも使ったプラグインは、SONAR付属のものだけです。チャンネル・ストリップ「ProChannel」は多用しましたし、ほとんど全部、ひと通りは使いました。
三柴:「Club BGM」は、昭和40年代の高級クラブで流れているBGMという設定で作った曲なんです。時代感と、当時の“高級クラブ”の上品さを出すために、バッハ全曲集の中から雰囲気が合う曲を探して、アレンジを加えました。中間部分で、映像の時間軸が飛んで、登場人物が酔っ払い出すんですね。だから音楽も、そこでスッと雰囲気が変わるように作っています。そうやって録音したものを、佐々木さんに「音を劣化させて、小さい音量で聴かせられるようにしてください」とお願いしたら、本当にバッハのレコードを再生しているかのような音に仕上げてくれました。
佐々木:ヒス・ノイズを混ぜたんです。そうしないと、音がクリアで、ツルツルしすぎるんですね。それでノイズ成分を上げて、さらにProChannelのコンプレッサーで軽く潰しました。すると少しハイ落ちするので、その分、EQでハイを持ち上げて調整しました。
佐々木:基本的には、空間系とProChannelのEQ、コンプレッサー、チューブ・サチュレーターを使ったくらいです。EQはトータル(マスター・チャンネル)でもかけていますが、INTEGRA-7のサウンド・クオリティだと、そもそもEQする必要はほとんどなくて、ハイファイすぎるから少しハイを削って質感を落とすとか、そういう使い方が多かったです。INTEGRA-7って、ひとつひとつの音色がすごく“立つ”ので、トラックをまとめても、ほとんど補正の必要がないんですよ。それでも、映像の時代感と音の質感のマッチングがしっくりこないという時は、だいたいProChannelのチューブ・サチュレーターをオンにしました。困った時は、必ずチューブ(笑)。まったく嫌な質感にならずにローファイになってくれるので、ProChannelがあれば、もう他は何も必要ないと思うくらい、大活躍でしたね。こういった作業まで、INTEGRA-7とSONARだけでやれたということは、とても楽でしたし、作業自体も楽しかったですね。
三柴:本当に、そう思います。ただ、先ほど佐々木さんが、僕のことを“オーケストラ・マニア”っておっしゃいましたけど、佐々木さんも、ホールでオーケストラの演奏を録音したり、いろんな生楽器の音を熟知されている方であって、だからこそできたという部分は、とても大きいんです。ミックスでも、ロックやポップスだけしか作ってないと分からないようなこと、例えば「バイオリン(の音像)は、普通はここにいる」とか、「ここにホルン(の音像)がいるのはおかしい」ということを、ちゃんと指摘してくれるんです。「コントラバスなら、こういう風に弾くでしょ?」とか、そういう耳を持っているからこそ、確かな音楽が作れるわけです。最近は、高品位なサンプリング音源がたくさんありますが、「それを持っているから、オーケストラはいらない」という話ではなく、そこは絶対に勘違いしないで欲しいですね。オーケストラの劇伴を作る際に、INTEGRA-7を導入することは大事なんだけれども、この音源の真価を発揮させるためには、打ち込みだけでなく、ある程度は手弾きで作っていくことも重要であって、そうすることで、本当の意味でのオーケストラ・サウンドが得られるんです。
佐々木:裏を返せば、そこが「THE 金鶴」の“強み”なのかなと思っています。これほどまでに生演奏をシミュレートした形でINTEGRA-7を使いこなせる人って、実はまだ、そんなにいないのではないかと思っていて。同じINTEGRA-7を使っていても、普通のキーボーディストや宅録の人たちと、「THE 金鶴」の音は、ひと味違っているんじゃないかな。そういう部分も、サウンド・トラックから聴き取って欲しいですし、INTEGRA-7が、そこまで表現してくれる音源だという証にもなるんじゃないかと考えています。

 『THE金鶴/THE金鶴』
“THE金鶴”の結成25周年記念アルバム
DDCH-2315 3,015
『THE金鶴/THE金鶴』
“THE金鶴”の結成25周年記念アルバム
DDCH-2315 3,015  『V.A./JAMMIN’ with CHOPIN』
“THE金鶴”がショパンのピアノ曲「雨だれ」で参加
VPCC-84441 2,700
『V.A./JAMMIN’ with CHOPIN』
“THE金鶴”がショパンのピアノ曲「雨だれ」で参加
VPCC-84441 2,700